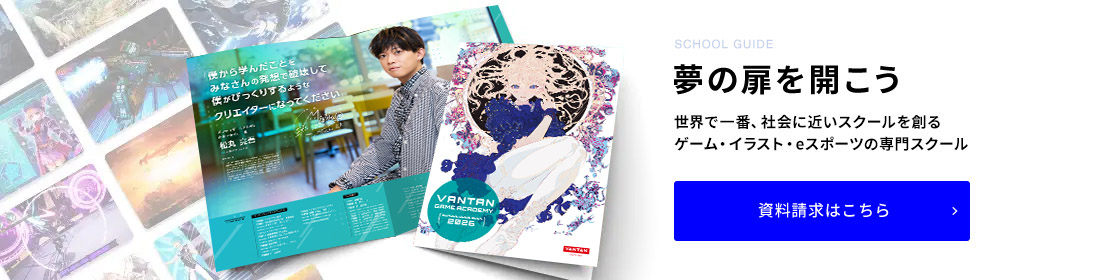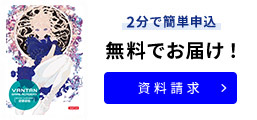学部・コース
「好き」を仕事に。理想の未来をバンタンで叶えよう。現役クリエイター講師による実践教育・充実した就職サポートでクリエイティブ業界を目指す!「学びたい」がきっと見つかるバンタンの全コース。

ゲーム学部
ゲーム業界と共に若き才能を育成。
実践力にこだわったカリキュラム。

eスポーツ学部
これからのeスポーツ業界を牽引する。
一流のプロフェッショナルを育成。